 最近読んだ陳舜臣著『紙の道』の中に興味深い場面があった。三蔵法師で知られている玄奘三蔵が天竺(インド)からおびただしい貝多羅の経を持ち帰るところである。当資料館の収蔵品の中には、紙はもとよりそれ以前の物でパピルス、パーチメント、タパ、アマテ等もあり、そして貝多羅もある。
最近読んだ陳舜臣著『紙の道』の中に興味深い場面があった。三蔵法師で知られている玄奘三蔵が天竺(インド)からおびただしい貝多羅の経を持ち帰るところである。当資料館の収蔵品の中には、紙はもとよりそれ以前の物でパピルス、パーチメント、タパ、アマテ等もあり、そして貝多羅もある。
インドではターラと呼ばれている多羅樹の葉を貝多羅という。その繊維は硬く棕櫚の葉を大きくした形になっている。椰子科の植物で木は20メートルくらいの高さまで育ち、特に湿気や虫に強いので紙以前の書写材料として葉が活用され、なかでも写経に多く使われた。
写真の経の作り方はまず、葉を切り取り、板を当てておよそ8センチ×60センチの大きさに切る。
それをあぶり、表と裏に鉄筆の様なもので文字を書く。書くは掻くから転用された言葉だが、この貝多羅の文字はまさに掻くといったほうがいいほど力のいる作業らしい。文字をつなげて書くと裂けてしまう葉でもある。その為一字ずつ丸い文字の書き方になっている。そこに油に煤をまぜたインクを流し込み、熱した砂で拭き取ることで文字が黒く残る。葉の中ほどに紐を通す穴を開け、一枚ずつ、めくれるように工夫されている。最後に漆で装飾した板で経をはさみ、穴に紐を通して止め、布に包む。
この紐を修多羅といって正確にきちんと束ねる事を意味する。その紐がゆるんでいる状態を「ふしだら」と言い仏教から来ている言葉だと知って驚いた。

核大したもの
が天竺(インド)から持ち帰ったのが
貝多羅に書かれている520
夾もの経であった。
夾は、「はさむ」の語意で
貝多羅の束をいう。
彼が(629年)中国を出発した時、この国にはすでに紙が開発されておよそ500年も経っていたが、天竺(インド)では紙はあまり普及していなかった時代でもあった。
資料館の
貝多羅の経は、どこの国のものでいつの時代のものかもはっきりしないが自然と気持ちをおだやかにさせてくれる文字の力に惹かれる。
それは丸く模様のようにも見えてきたりして、あれこれ思いをめぐらしてしまう。おそらく南方の気候と風土に包まれて経を書く人もおおらかに育っていったのだろう。澄んだ青い空にそびえる仏塔の近くに、
貝多羅の木が寄り添う様に立っているのが目に浮ぶ。
※資料館の貝多羅経は厚みがないが、一般の貝多羅経はかなり厚い物である。
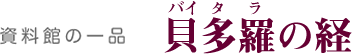
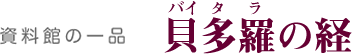
 最近読んだ陳舜臣著『紙の道』の中に興味深い場面があった。三蔵法師で知られている
最近読んだ陳舜臣著『紙の道』の中に興味深い場面があった。三蔵法師で知られている