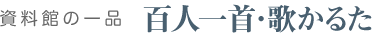
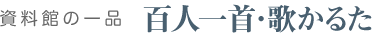
 百人一首と言えば、かるたとして私達の暮らしに馴染み、特にお正月の風物詩になっています。それは飛鳥時代の天智天皇から鎌倉時代の順徳院まで、600年の間の100人の代表的な和歌を選んで年代順に歌集にしたもので、選者は藤原定家(1162年〜1241年)。
藤原定家の生きていた時代は政権が貴族から武士に移っていく激動の時代だったので、王朝文化の最後の輝きを感じ取って万感の想いで自らも歌を詠み、歌を選んだのでしょう。歌は季節とつながり又人間関係が絡まりあって微妙な感情を表現しています。
百人一首と言えば、かるたとして私達の暮らしに馴染み、特にお正月の風物詩になっています。それは飛鳥時代の天智天皇から鎌倉時代の順徳院まで、600年の間の100人の代表的な和歌を選んで年代順に歌集にしたもので、選者は藤原定家(1162年〜1241年)。
藤原定家の生きていた時代は政権が貴族から武士に移っていく激動の時代だったので、王朝文化の最後の輝きを感じ取って万感の想いで自らも歌を詠み、歌を選んだのでしょう。歌は季節とつながり又人間関係が絡まりあって微妙な感情を表現しています。
その百人一首が歌かるたとして作られたのは江戸時代の初め。
当資料館の歌かるたは、江戸時代後期のもので、畳紙に包まれ古びた漆の箱に納められています。絵も歌もおぼろげにしか分からないくらいかなり使われていて、時代を感じさせます。豪華とは言えないまでも、読み札は、木版摺りに色をさした素朴な絵が面白く、取り札にも銀箔の砂子を散らし、味わいのあるかな文字でまとめられています。裏にも銀箔が押してあって、見えない所にまでこだわりがあるのが心憎いばかり。
さて、歌かるたの中から紙に関わりのある歌を紹介しましょう
百人一首二番目の歌
春すぎて夏来にけらし白妙 の衣干すてふ天の香具山 持統天皇(645年〜702年)※
ある朝、持統天皇が香具山を見ると白い布が干してあった。それは周りの景色 に良く映え目にしみるようなうつくしさで、夏の訪れが感じられた。